

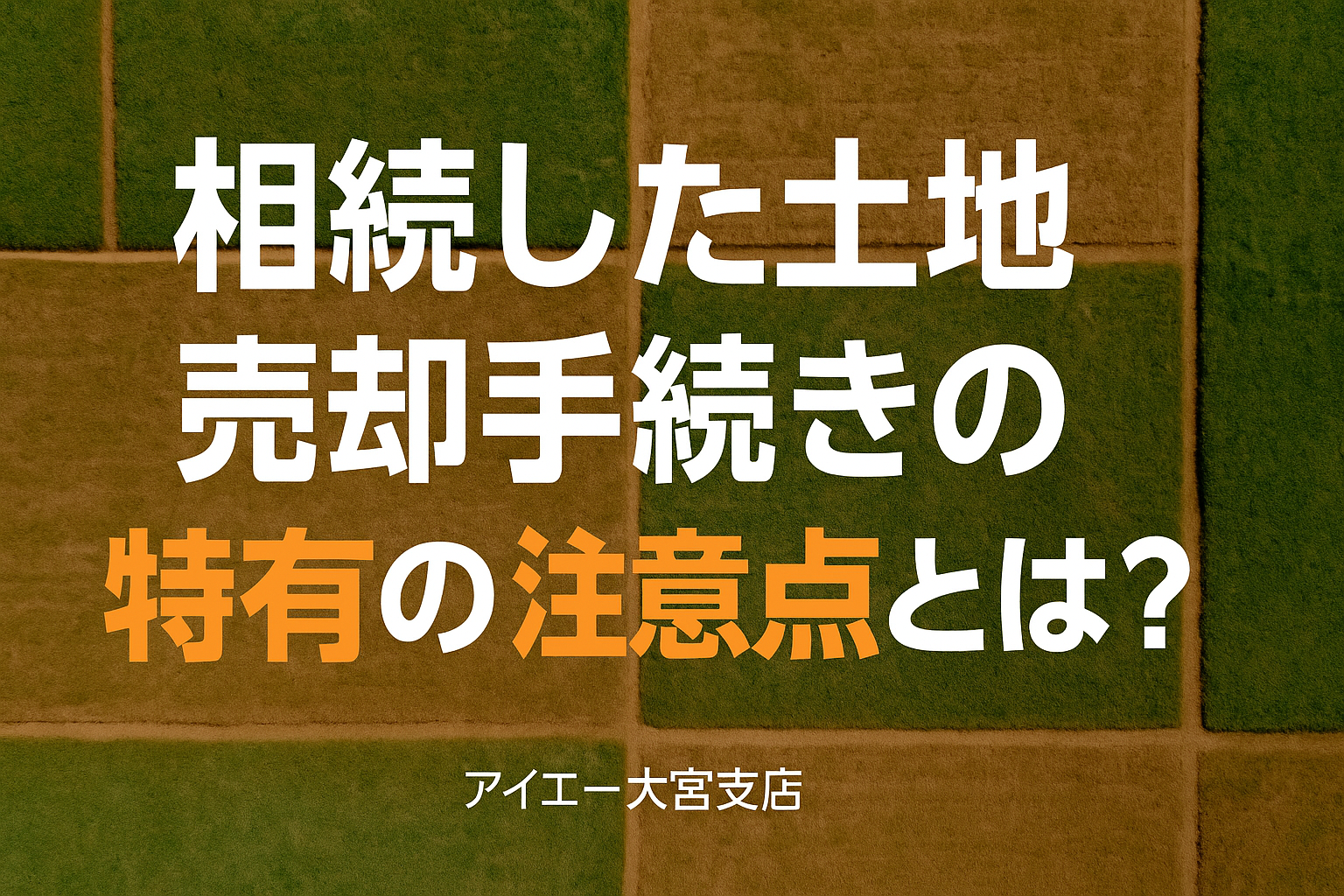
「親から土地を相続したけれど、使う予定もないし売却したい。でも、何から始めればいいのだろう…」
「通常の名義変更や売却とは違う、特別な手続きや注意点があるのでは?」
さいたま市大宮区を中心に不動産売買をお手伝いする株式会社アイエーの大宮支店です。この度は、大切なご家族様がお亡くなりになられたとのこと、心よりお悔やみ申し上げます。
相続は、誰にとってもいつかは訪れるものですが、悲しみに暮れる間もなく、複雑な手続きに直面し、戸惑いや不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。特に、相続した土地の売却は、ご自身で購入した不動産を売るのとは異なり、特有の手順や法律、税金の知識が求められます。
この記事では、不動産のプロである私たちが、相続した土地の売却を検討されている皆様の不安を解消すべく、手続きの流れから特有の注意点、節税のポイントまで、どこよりも分かりやすく徹底的に解説します。
この記事を最後までお読みいただければ、相続した土地を円満かつ有利に売却するための知識が身につき、自信を持って第一歩を踏み出せるはずです。
冒頭でも触れましたが、相続した土地の売却をスムーズに進め、最終的に「売ってよかった」と心から思える結果を得るためには、押さえるべき大きなポイントが2つあります。
なぜこの2つが特に重要なのでしょうか。
ご自身で購入した不動産であれば、所有者は当然あなた一人であり、売却の意思決定から手続きまでスムーズに進められます。しかし、相続不動産の場合、スタートラインが全く異なります。
まず、土地の登記名義が亡くなったご家族(被相続人)のままです。法律上、所有者でなければ不動産を売却することはできません。そのため、売却活動を始める大前提として、相続人の誰かの名義に土地の所有権を移す「相続登記」という手続きが絶対に必要になります。相続人が複数いる場合は、その前に「誰が土地を相続するのか」という遺産分割協議も必要となり、ここが最初の関門です。
そして、無事に売却できたとしても、それで終わりではありません。土地を売って得た利益(譲渡所得)に対しては、翌年に税金(所得税・住民税)が課せられます。この税金をいかに抑えるかが、手元に現金を残すための非常に重要なポイントになります。相続不動産の売却には、知っているか知らないかで納税額が数百万円単位で変わる可能性のある、強力な節税特例が存在します。このチャンスを逃さないためには、売却前から正しい知識を身につけておく必要があるのです。
この記事では、この「相続登記」と「税金対策」を2大テーマと位置づけ、具体的な手続きの流れに沿って、皆様がつまずきやすいポイントを丁寧に解説していきます。
空き家・空き店舗から市街化調整区域まで。なんでもご相談ください!
「普通の土地売却と何がそんなに違うの?」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。相続した土地の売却が特殊である理由は、大きく分けて以下の3つです。
これらの違いを理解することが、相続した土地の売却を成功させる第一歩となります。
それでは、具体的な手続きの流れを見ていきましょう。まずは売却活動を始める前、準備段階で必ずクリアしなければならないステップと、その注意点です。
相続が開始したら、まず最初に被相続人が「遺言書」を遺していないかを確認します。遺言書がある場合、原則としてその内容に従って遺産分割が行われるため、その後の手続きが大きく変わります。
遺言書で土地を相続する人が指定されていれば、その人が単独で相続登記の手続きを進めることができます。
遺言書がない場合、または遺言書で指定されていない財産がある場合は、法律で定められた相続人(法定相続人)全員で遺産を分けることになります。そのため、「誰が相続人なのか」を正確に確定させる必要があります。
これを証明するために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)と、相続人全員の現在の戸籍謄本を取得します。前妻との間に子がいる場合や、養子縁組をしている場合など、把握していなかった相続人が判明することもあるため、この作業は非常に重要です。
同時に、売却対象の土地以外にどのような財産(預貯金、有価証券、他の不動産など)や債務(借金など)があるのか、財産調査も行い、相続財産の全体像を把握します。
相続人が複数いる場合、法定相続分どおりに共有名義で相続することも可能ですが、売却を前提としているなら共有名義は絶対に避けるべきです。なぜなら、共有名義の不動産を売却するには、共有者全員の同意と実印、印鑑証明書が必要となり、一人でも反対したり、連絡がつかなくなったりすると売却できなくなってしまうからです。
そこで、相続人全員で話し合い、「誰がその土地を相続するのか」を決定します。これが「遺産分割協議」です。
例えば、相続人が子A、子Bの2人で、土地を売却して現金を分けたい場合、以下のような方法が考えられます。
話し合いがまとまったら、その内容を法的な書面として残すために「遺産分割協議書」を作成します。この書類には、相続人全員が署名し、実印を押印します。印鑑証明書も添付する必要があり、後の相続登記や税務申告で必須となる非常に重要な書類です。
遺産分割協議が整い、土地を相続する人が決まったら、法務局で土地の名義を被相続人から相続人へ変更する「相続登記」の手続きを行います。
前述の通り、この相続登記を完了させなければ、法的に土地の所有者とは認められず、売却することはできません。
【重要】2024年4月1日から相続登記が義務化されました!
この法改正により、相続登記は「いつかやればいい」ものではなく、「必ずやらなければならない」手続きとなりました。売却する・しないにかかわらず、不動産を相続したら速やかに相続登記を行いましょう。
相続登記は自分で行うことも可能ですが、必要書類が多岐にわたり複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。
空き家・空き店舗から市街化調整区域まで。なんでもご相談ください!
相続登記が完了し、土地の名義がご自身のものになったら、いよいよ売却活動のスタートです。
土地の売却には、様々な費用がかかります。手元にいくら残るのかを正確に把握するためにも、どのような費用が必要かを知っておきましょう。
| 費用の種類 | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う成功報酬 | 売買価格の3% + 6万円 + 消費税(上限) |
| 印紙税 | 売買契約書に貼る印紙代 | 売買価格により1万円~6万円程度 |
| 登記費用 | 抵当権抹消費用、住所変更登記費用など | 数万円程度(司法書士報酬含む) |
| 測量費用 | 土地の境界を確定させるための費用 | 35万円~80万円程度(土地の状況による) |
| 建物解体費用 | 古家付き土地の場合、更地にする費用 | 100万円~300万円程度(構造・規模による) |
| その他 | 遺品整理費用、ハウスクリーニング費用など | 実費 |
特に、土地の境界が不明確な場合は、隣地所有者とのトラブルを防ぎ、土地の価値を正しく評価してもらうために「確定測量」を行うことが強く推奨されます。費用はかかりますが、結果的にスムーズで高値での売却に繋がります。
また、古家が建っている場合は、「古家付き土地」として売るか、「更地」にして売るかを不動産会社と相談して決めましょう。解体費用はかかりますが、一般的に更地の方が買い手は見つかりやすい傾向にあります。
売却のパートナーとなる不動産会社選びは、最も重要なステップと言っても過言ではありません。ここで大切なのは、「相続案件の実績が豊富な不動産会社」を選ぶことです。
相続不動産の売却は、前述の通り税金や法律が複雑に絡み合います。
「この土地を売却した場合、税金の特例は使えますか?」
「兄弟で円満に財産を分けるには、どんな方法がありますか?」
といった相続特有の相談に対して、的確なアドバイスができる会社を選びましょう。弁護士や税理士、司法書士といった専門家との連携がしっかりしている不動産会社であれば、さらに心強いです。
まずは複数の会社に査定を依頼し、査定価格の根拠を明確に説明してくれるか、親身に相談に乗ってくれるか、相続に関する知識は豊富か、といった点を見極めましょう。私たち株式会社アイエー 大宮支店では、相続に関するご相談も数多く承っております。無料査定も実施しておりますので、お気軽にお声がけください。
不動産会社と媒介契約を結び、買主が見つかったら、いよいよ売買契約と決済(引渡し)です。
相続した土地の場合、売主様自身がその土地について詳しく知らないケースが多いため、「契約不適合責任」に注意が必要です。
契約不適合責任とは、売買した土地に契約書の内容に適合しない欠陥(例:地中にコンクリートガラなどの埋設物があった、土壌が汚染されていた)が見つかった場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。
買主は売主に対して、追完請求(修理など)、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除などを求めることができます。
このような事態を防ぐためにも、事前に土地の状態をできる限り調査し、把握している問題点(もしあれば)は全て不動産会社に伝え、契約書や重要事項説明書に明記してもらうことが重要です。
「知らなかった」では済まされないケースもあるため、正直に情報開示することが、後のトラブルを防ぐ最善策となります。
空き家・空き店舗から市街化調整区域まで。なんでもご相談ください!
無事に土地の売却が完了したら、翌年の2月16日~3月15日の間に、ご自身で確定申告を行い、売却で得た利益に対する税金(譲渡所得税)を納める必要があります。ここが手元に残る金額を大きく左右する最後の関門です。
譲渡所得は以下の計算式で算出します。
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
この譲渡所得に対して、土地の所有期間に応じた税率が課せられます。
ここで注意したいのが「取得費」です。被相続人が土地を購入したときの売買契約書などが見つからず、取得費が不明な場合、売却価格の5%を概算取得費として計算することになります。こうなると取得費が非常に低く見積もられ、譲渡所得が大きくなり、結果として税額が跳ね上がってしまいます。古い契約書でも大切に探しておきましょう。
相続した土地の売却では、税負担を大幅に軽減できる2つの重要な特例があります。ご自身の状況に合わせて、どちらか有利な方を選択して適用しましょう。(※併用はできません)
この特例は要件が非常に細かく複雑です。ご自宅が対象になるか不明な場合は、必ず税務署や専門家に確認しましょう。
相続の状況はご家庭によって様々です。ここでは、よくある特殊なケースとその注意点について解説します。
相続した土地が、宅地ではなく「農地(田・畑)」だった場合、売却には注意が必要です。
農地を農地として売却する場合は、買主が農業従事者である必要があり、農業委員会の許可が必要です。農地を宅地など他の用途に転用して売却(農地転用)する場合も、都道府県知事等の許可が必要となり、手続きが複雑になります。
また、「市街化調整区域」内にある土地は、原則として建物を建てることができないなど、開発が厳しく制限されています。そのため、買い手が限られ、売却が難しくなる傾向があります。
こうした特殊な土地の売却は、専門的な知識とノウハウが不可欠です。通常の不動産会社では対応が難しいケースもあるため、これらの土地の取り扱い実績が豊富な会社に相談しましょう。
ここまでお読みいただき、相続した土地の売却がいかに複雑で、専門的な知識を要するかお分かりいただけたかと思います。もちろん、ご自身で全ての手続きを行うことも不可能ではありませんが、多大な時間と労力がかかり、ミスやトラブルのリスクも伴います。
相続案件に強い不動産会社に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
空き家・空き店舗から市街化調整区域まで。なんでもご相談ください!
Q1. 相続した土地の売却は、いつまでに行うべきですか?
A1. 法律上の売却期限はありませんが、税金の特例を考慮すると2つのタイミングが重要です。①「相続税の取得費加算の特例」を使いたい場合は、相続開始から3年10ヶ月以内。②「空き家の3,000万円特別控除」を使いたい場合は、相続開始から3年が経過する年の年末までです。これらの特例を活用したい場合は、期限から逆算して早めに準備を始めることをお勧めします。
Q2. 兄弟と共有名義で土地を相続してしまいました。売却は可能ですか?
A2. 可能です。ただし、前述の通り、売却するには共有者である兄弟全員の同意と、売買契約書への署名・捺印(実印)、印鑑証明書の提出が必須となります。一人でも反対すれば売却はできません。もし意見がまとまらない場合は、ご自身の持分だけを第三者に売却することも理論上は可能ですが、買い手を見つけるのは非常に困難です。まずは全員でよく話し合うことが大切です。
Q3. 売却代金は、いつもらえるのですか?
A3. 売却代金は、一般的に2回に分けて支払われます。1回目は「売買契約時」に手付金として売買代金の5%~10%程度、2回目は物件の最終的な引渡し(決済)時に残りの全額が支払われます。受け取った代金は、遺産分割協議書の内容に基づいて、他の相続人と分配することになります。
Q4. 査定価格は、不動産会社によって違いますか?
A4. はい、査定価格は不動産会社によって異なる場合があります。各社が持つ販売実績や顧客データ、得意なエリアや物件種別などが異なるためです。そのため、1社だけでなく、2~3社の不動産会社に査定を依頼し、その価格の根拠を比較検討することをお勧めします。ただし、高すぎる査定額には注意が必要です。契約欲しさに相場より高い価格を提示するケースもあるため、なぜその価格なのか、納得できる説明を求めることが重要です。
Q5. 相続した土地に借金(抵当権)が残っているようです。どうすればいいですか?
A5. 被相続人が住宅ローンなどを組んでおり、土地に抵当権が設定されている場合は、売却代金を使ってその借金を完済し、抵当権を抹消する手続きが必要です。通常、物件の引渡し(決済)の日に、買主から受け取った代金で金融機関に返済し、同日中に司法書士が抵当権抹消登記を申請します。売却価格がローン残高を下回る場合は、自己資金で補填する必要があります。
Q6. 相続税の申告と、土地売却後の確定申告は別物ですか?
A6. はい、全くの別物です。相続税の申告は、相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署に行うものです。一方、土地売却後の確定申告は、土地を売って利益(譲渡所得)が出た場合に、売却した年の翌年2月16日~3月15日の間に行うものです。両者は申告の目的も時期も異なりますので、混同しないように注意しましょう。
Q7. 遠方に住んでいて、相続した土地の管理ができません。すぐに売却した方がいいですか?
A7. 管理が難しい場合は、早めに売却を検討することをお勧めします。土地は所有しているだけで固定資産税がかかりますし、雑草が生い茂るなど管理を怠ると、近隣トラブルに発展する可能性もあります。近年は「特定空家」に指定されると固定資産税の優遇が受けられなくなるなど、所有者責任がより厳しく問われるようになっています。負の資産(負動産)となってしまう前に、専門家へ相談しましょう。
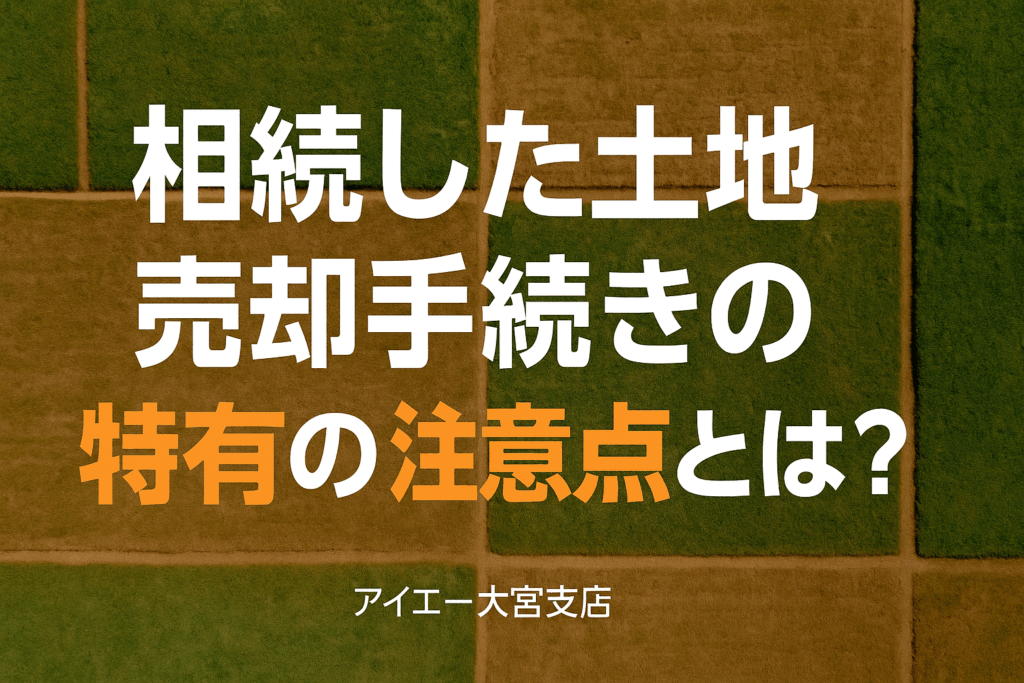
今回は、相続した土地の売却における特有の注意点について、手続きの流れに沿って詳しく解説しました。
相続不動産の売却は、通常の売却に比べてやるべきことが多く、法律や税金の専門知識も必要となるため、ご自身だけで進めるのは非常に大変です。特に、相続人が複数いる場合は、感情的な対立が生まれ、話し合いが難航してしまうケースも少なくありません。
そんな時、相続案件の経験が豊富な不動産会社は、皆様の心強い味方となります。法的な手続きのサポートはもちろん、相続人間の円滑なコミュニケーションのお手伝いや、税理士・司法書士といった専門家との橋渡し役も担うことができます。
大切なのは、一人で抱え込まず、分からないことは専門家に相談しながら、一つひとつ着実にステップを進めていくことです。
株式会社アイエー 大宮支店では、これまで数多くの相続不動産の売却をお手伝いしてまいりました。さいたま市エリアの不動産市場に精通したスタッフが、お客様一人ひとりのご事情に寄り添い、法律や税金の専門家とも連携しながら、最善の売却プランをご提案いたします。
「何から始めたらいいか分からない」「うちの場合は税金の特例が使えるの?」など、どんな些細なご相談でも構いません。無料査定も秘密厳守で承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。皆様が安心して、新たな一歩を踏み出すためのお手伝いができれば幸いです。
無料土地査定のフォームに入力するのも面倒なあなたにおすすめ!LINEを使った土地のお悩み相談もあります。営業時間にオペレーターが直接返信いたします。

正確な価格が知りたい方や、直接担当者と話がしたい方も、もちろん電話相談受付中です。書類の取り寄せ、実際に現地に足を運び、正確に土地査定いたします。
近年早く土地を売りたいお客様が増えております。なるべく早く対応させていただきますが、一つ一つを丁寧正確にと対応していくとお待たせしてしまうことがありましたので、予約することをおすすめします。
